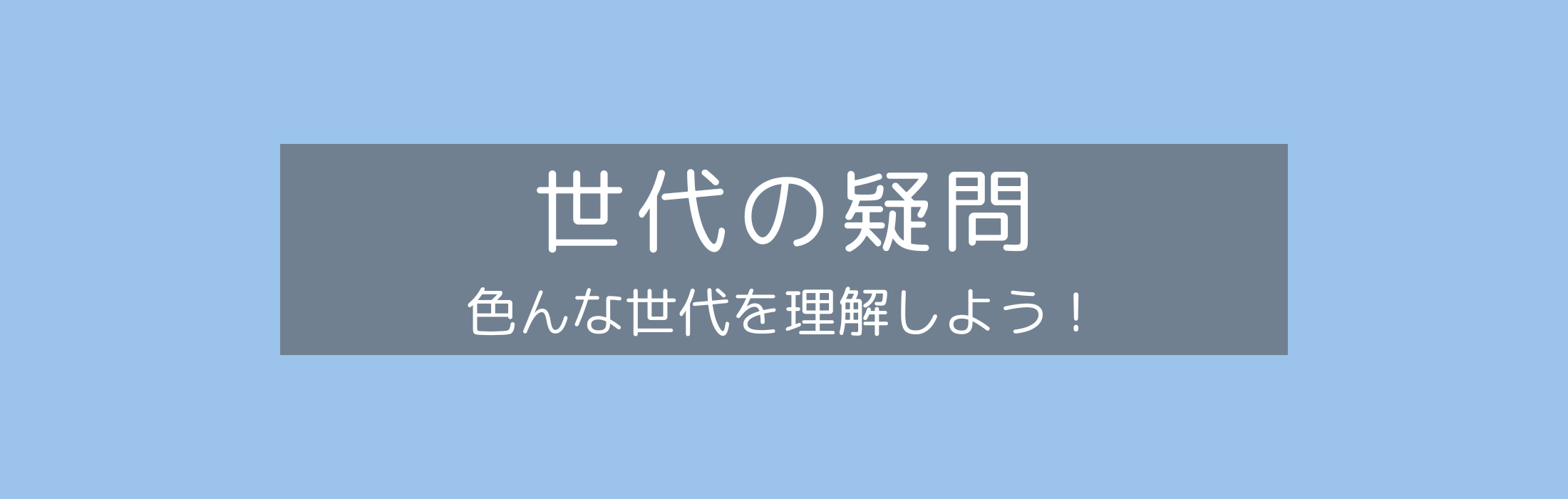あなたは「1996年生まれは何世代に属するの?」と気になったことはありませんか?実は、1996年生まれは「Z世代」と呼ばれる世代カテゴリーに属しています。Z世代は1996年から2012年に生まれた世代とされており、デジタルネイティブとして注目を集めています。
この記事では、1996年生まれがZ世代に属する意味や特徴、他の世代との違い、そして同じ年に生まれた有名人まで、詳しく解説していきます。世代によって価値観や消費行動が大きく異なることから、マーケティングの世界でも「Z世代」は重要なターゲット層として注目されています。あなたやあなたの周りの1996年生まれの人の特性を理解する一助になるでしょう。
記事のポイント!
- 1996年生まれはZ世代(ジェネレーションZ)に属していることを明確に理解できる
- Z世代特有の価値観や消費行動の特徴について詳しく知ることができる
- ミレニアル世代とZ世代の違いと、1996年生まれが境界に位置する意味を理解できる
- 1996年生まれの有名人や、Z世代をターゲットとしたマーケティング手法について知ることができる
1996年生まれは何世代に属するのか
- 1996年生まれはZ世代に属している
- Z世代の定義は1996年~2012年生まれが一般的
- Z世代が”Z”と呼ばれる理由はアルファベット順
- 1996年生まれは平成8年生まれで2025年に29歳
- Z世代の前はミレニアル世代(Y世代)との比較
- 世代の区分けは諸説あり明確な線引きは難しい
1996年生まれはZ世代に属している
1996年生まれの方は、「Z世代」と呼ばれる世代カテゴリーに属しています。Z世代は、デジタルテクノロジーが急速に発展した時代に生まれ育った世代を指し、「デジタルネイティブ」と呼ばれることもあります。
Z世代は別名「ポストミレニアル世代」とも呼ばれており、インターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育った特徴があります。1996年生まれの方々は、このZ世代の最初の年に当たるため、Z世代の中でも先駆け的な存在といえるでしょう。
調査の結果、Z世代が注目される理由として、世界的に見るとその購買力が増加していることが挙げられます。2020年時点で世界のZ世代が占める割合は約24%で、その購買力は15兆円ともいわれています。アジア太平洋地域でも、2025年までにZ世代が人口の約25%となる見込みです。
1996年生まれの方々は、2025年現在で29歳を迎え、社会人としての地位を確立しつつある年代です。Z世代の中でも比較的早く生まれた彼らは、Z世代特有の価値観や行動様式を社会に浸透させる先導者的な役割を担っていると言えるでしょう。
Z世代であることを理解することで、自分自身の行動パターンや価値観をより客観的に捉えることができます。特に1996年生まれの方は、Z世代の特徴とミレニアル世代の特徴の両方を持ち合わせている可能性もあり、その独自のポジションは興味深いものがあります。
Z世代の定義は1996年~2012年生まれが一般的

Z世代の定義については様々な見解がありますが、最も一般的な定義では1996年から2012年までに生まれた世代を指します。調査の結果、アメリカのコンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーもこの定義を採用しています。
この定義に基づくと、2025年現在ではZ世代は約13歳から29歳の年齢層に該当します。この世代区分によれば、小学生高学年から20代後半までの幅広い年齢層が含まれることになります。これほど幅広い年齢層をひとくくりにすることには限界もありますが、共通する時代背景や価値観を持つことから、マーケティングなどの分野では有用な区分とされています。
Z世代の次の世代は「α(アルファ)世代」と呼ばれており、2013年以降に生まれた世代を指します。α世代は、Z世代よりもさらにデジタル技術が進化した環境で育っており、「SNSネイティブ」とも呼ばれています。
1996年生まれはZ世代の最初の年に当たるため、Z世代の特徴を持ちながらも、前の世代であるミレニアル世代の特徴も併せ持つ「カスプ世代」(世代の境界に位置する世代)であるという見方もあります。このような境界に位置する年代の方々は、両方の世代の特徴を持ち合わせていることが多いとされています。
ただし、世代の区分はあくまで一般的な傾向を示すものであり、同じ年に生まれた人の中でも育った環境や個人の経験によって、価値観や行動パターンには大きな差異があることを忘れてはいけません。
Z世代が”Z”と呼ばれる理由はアルファベット順
Z世代が「Z」と名付けられた理由は、単純にアルファベット順に従ったためです。調査の結果、その前の世代がX世代(1965年~1979年生まれ)、Y世代またはミレニアル世代(1980年~1995年生まれ)と呼ばれていたため、論理的に次の世代は「Z」となりました。
この命名方法は単に便宜的なものですが、Z世代がアルファベットの最後の文字であることから、「最後の世代」というニュアンスも含まれていると解釈する人もいます。しかし実際には、Z世代の次の世代は「α(アルファ)世代」と名付けられており、ギリシャ文字を用いて新たな命名サイクルが始まっています。
世代名は社会学者やマーケティング専門家によって作られた概念であり、歴史的な出来事や社会的変化、技術の発展などに基づいて区分されています。Z世代の場合は、インターネットやスマートフォンの普及、ソーシャルメディアの台頭という技術的な転換点を背景に名付けられました。
このような世代区分は、マーケティングや社会研究の分野で活用されることが多く、各世代の特徴を理解することで、異なる年代の人々との意思疎通やビジネスアプローチを考える上で役立ちます。
ただし、これらの名称や区分はあくまでも便宜上のものであり、すべての人がその世代の特徴に完全に当てはまるわけではありません。特に1996年生まれのような世代の境界に位置する方々は、両世代の特性を併せ持つことが多いでしょう。個人の価値観や行動パターンは、世代だけでなく、家庭環境や教育、文化的背景など様々な要因に影響されるものです。
1996年生まれは平成8年生まれで2025年に29歳
1996年生まれの方は、日本の元号では平成8年生まれにあたります。2025年(令和7年)現在では、すでに29歳になっている方か、もうすぐ29歳を迎える方です。干支では「子(ね)年」であり、十二支の最初を担う年に生まれた方々です。
1996年には様々な社会的出来事がありました。Windows 95の日本語版が発売され、O-157食中毒事件が発生し、アトランタオリンピックが開催されました。こうした時代背景のもとに生まれた1996年生まれの方々は、物心がついた頃にはインターネットが一般家庭に普及し始め、デジタル技術の発展とともに成長してきました。
1996年生まれの方々の人生の節目には、様々な社会的変化や出来事が重なっています。中学校を卒業する頃には東日本大震災(2011年)を経験し、高校を卒業する頃には消費税が8%に引き上げられました(2014年)。大学進学後には、イギリスのEU離脱決定(2016年)などの国際的な出来事があり、場合によっては就職活動への影響も懸念されました。
このように、1996年生まれの方々は人生の節目に大きな社会変化や出来事を経験してきたことから、時に「悪魔の世代」と呼ばれることもあります。しかし実際には、これらの経験を通じて柔軟性や適応力を身につけた世代とも言えるでしょう。
2025年現在、1996年生まれの方々は20代後半という年齢を迎え、多くの方がキャリアの方向性を定め始める時期にあります。Z世代の中でも早く社会に出た彼らは、Z世代の価値観や行動様式を社会に浸透させる先駆者的な役割も担っています。
Z世代の前はミレニアル世代(Y世代)との比較
Z世代の前に位置するのは「ミレニアル世代」または「Y世代」と呼ばれる世代です。調査の結果、ミレニアル世代は一般的に1980年から1995年までに生まれた人々を指し、2025年現在では約30歳から45歳の年齢層に該当します。
ミレニアル世代とZ世代には、いくつかの共通点と相違点があります。共通点としては、両世代ともワーク・ライフ・バランスを重視し、環境問題や社会課題に関心が高く、多様性を尊重する傾向があります。しかし、デジタル技術との関わり方には大きな違いが見られます。
ミレニアル世代は「デジタルパイオニア」とも呼ばれ、青年期にデジタル技術の急速な発展を経験しました。彼らは子供時代にはアナログ環境で過ごし、その後デジタル技術が普及する変化を体験した世代です。一方、Z世代は「デジタルネイティブ」と呼ばれ、生まれた時からデジタル環境が当たり前の時代に育った世代です。
消費行動においても違いが見られます。ミレニアル世代が「コト消費」(体験を重視する消費)や「トキ消費」(時間を重視する消費)を好む傾向があるのに対し、Z世代はより「イミ消費」(意味のある消費)や「エモ消費」(感情を動かされる消費)を重視する傾向があります。
また、調査によるとZ世代のほうがミレニアル世代よりも節約志向が強く、貯蓄や投資への意識が高い傾向にあります。これは、Z世代が不確実性の高い時代に生まれ育ち、将来に対する不安を抱えていることが影響していると考えられます。
1996年生まれの方々は、ミレニアル世代とZ世代の境界に位置しているため、両方の世代の特徴を併せ持っていることが多いでしょう。このような世代の狭間に生まれた方々は、時に「ゼニアル世代」(Z世代とミレニアル世代の融合)と呼ばれることもあります。
世代の区分けは諸説あり明確な線引きは難しい
世代の区分けについては、研究機関や調査会社によって微妙な違いがあることを理解しておく必要があります。Z世代の始まりについても、1995年とする見解や1997年とする見解もあり、明確な合意は存在しません。調査の結果、最も一般的な定義とされる1996年~2012年もあくまで目安であり、絶対的なものではありません。
このような世代区分の違いは、各研究機関や調査会社が重視する社会的・技術的な転換点の解釈によるものです。例えば、インターネットの普及やスマートフォンの登場、ソーシャルメディアの台頭などを、どの時点で世代を分ける重要な転換点と見なすかによって、区分けが異なってきます。
日本独自の世代区分としては、「ゆとり世代」(1987年~2004年頃生まれ)や「さとり世代」(1996年~2005年頃生まれ)といった表現も存在します。1996年生まれの方は、こうした日本独自の世代区分でも境界に位置していることが多く、複数の世代的特徴を持ち合わせている可能性があります。
重要なのは、これらの世代区分はあくまで社会学的な概念であり、個人の性格や価値観を完全に規定するものではないということです。同じ年に生まれた人でも、育った環境や個人的な経験によって、価値観や行動パターンには大きな違いがあります。
世代区分は固定的なラベルとしてではなく、その時代の社会的・技術的背景を理解するための一助として捉えるのが適切です。1996年生まれの方々は、Z世代の始まりとしての特性を持ちながらも、個人としての独自性や多様性を持っています。そして、世代の枠を超えた共通の価値観や関心事を持つ人々との繋がりもまた重要です。
1996年生まれを含むZ世代の特徴とマーケティング活用法
- Z世代はデジタルネイティブの真のSNS世代
- Z世代の価値観は多様性と環境問題への関心が高い
- Z世代の消費行動は「エモ消費」「イミ消費」が特徴的
- Z世代の情報収集はGoogleより「タグる」「タブる」が主流
- Z世代向けのマーケティング手法は従来とは異なる
- 1996年生まれの有名人は様々な分野で活躍中
Z世代はデジタルネイティブの真のSNS世代
Z世代、特に1996年生まれの人々は、真のデジタルネイティブ世代として知られています。調査の結果、Z世代はインターネットやデジタルデバイスが日常生活に完全に組み込まれた環境で育った最初の世代です。彼らは物心がついた時からデジタル技術に囲まれ、それを直感的に使いこなす能力を持っています。
特にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)との関わりが深いのがZ世代の特徴です。1996年生まれの方々が中高生だった2010年代前半には、FacebookやTwitter、LINEなどのSNSがすでに普及していました。そして大学生の頃にはInstagramやSnapchat、後にTikTokなども人気となり、これらのプラットフォームを使いこなしてきました。
Z世代のインターネット利用時間の内訳を見ると、約35%が動画共有サービス(YouTubeなど)、約28%がSNS、約15%がゲームとなっています。特にSNSは単なるコミュニケーションツールではなく、情報収集や自己表現の場としても活用されています。
1996年生まれのZ世代は、デジタルデバイスの使用においても特徴的です。パソコンからスマートフォンへの移行期を経験しており、両方のデバイスを使いこなす能力を持っています。スマートフォンの普及率がガラケーを上回ったのは2013年とされており、1996年生まれの方々が高校3年生の頃です。
デジタルネイティブであることは、単に技術を使いこなせるということだけではなく、デジタル空間での人間関係の構築やアイデンティティの形成、情報の取捨選択など、独自の感覚や価値観を持っていることを意味します。これは職場や社会での行動様式や消費行動にも大きな影響を与えており、新しい形の社会参加や経済活動を生み出す原動力となっています。
Z世代の価値観は多様性と環境問題への関心が高い
Z世代の顕著な特徴として、多様性に対する理解と尊重の姿勢が挙げられます。調査の結果、Z世代の8割が「多様性は大切だと思う」と回答しており、性別、年齢、国籍、価値観、ライフスタイルなどの違いを自然に受け入れる傾向にあることがわかっています。これは学校教育でSDGsやダイバーシティについて学んだ世代であることも影響していると考えられます。
また、Z世代は環境問題や社会課題に対する関心も非常に高いことが特徴です。SHIBUYA109 lab.の調査によると、Z世代の70%以上が社会的課題を解決する取り組みを実施しており、67.7%が社会的課題に取り組む企業に対してポジティブな印象を持っていることがわかっています。
1996年生まれを含むZ世代は、幼少期から地球温暖化や環境破壊についての教育を受けてきました。また、東日本大震災や原発事故などの大きな社会問題を中学卒業時に経験しており、社会や環境に対する問題意識が高いのも特徴です。
Z世代の価値観は消費行動にも反映されています。「エシカル消費」と呼ばれる、社会や環境に配慮した製品を選ぶ購買行動が見られます。また、サステナブル(持続可能)な選択を好む傾向があり、環境に優しい商品や社会的課題の解決に取り組んでいる企業の商品を選ぶことが多いです。
ただし、Z世代はまだ若く学生も多いため、使えるお金が他の世代と比べて少ないという現実もあります。そのため、エシカルな製品であっても価格プレミアムを許容する割合は他の世代と変わらないという調査結果もあります。理想と現実のバランスを取りながら、自分たちの価値観を実現しようとしている世代だと言えるでしょう。
Z世代の消費行動は「エモ消費」「イミ消費」が特徴的
Z世代の消費行動を特徴づけるのが「エモ消費」と「イミ消費」です。調査の結果、「エモ消費」とは「感情を動かされる」消費行動のことで、具体例としては「昭和レトロな喫茶店でクリームソーダを飲む」「フィルム付カメラを買って撮影する」といった行動が挙げられます。これは単なる物の所有ではなく、その体験から得られる感情や思い出を重視する消費のあり方です。
一方、「イミ消費」は「意味のある消費」を指し、例えば「被災地を応援するためにその地域の産品を購入する」といった社会的意義や目的を持った消費行動です。Z世代は消費を通じて自分の価値観を表現したり、社会に貢献したりする傾向が強いと言えるでしょう。
エモ消費の3要素は「共感性」「ハッピー」「シェア」とされています。単に商品を購入するだけでなく、その体験に共感し、幸福感を得て、それをSNSなどで他の人と共有することが重要な要素となっています。特に、インスタグラムなどでシェアすることを前提とした消費行動が多いのもZ世代の特徴です。
Z世代はネットショッピングが日常に普及している環境で育ってきました。購入する前にはスマートフォンで徹底的にリサーチする「ネタバレ消費」が常態化しており、失敗なく、効率的に買い物をしたいという欲求が強いです。このようなインターネットを活用して欲しい情報を集めるリテラシーの高さもZ世代の特徴といえます。
ブランド選びにおいては、Z世代は一方で人気の高いブランドを好む傾向がありながら、他方では他人とは違う差別化できるブランドも求めるという、一見矛盾した特徴を持っています。企業側からすれば、マス向けでありながらも個性的であるという難しいバランスが求められます。パーソナライゼーションや限定商品、他ブランドとのコラボレーションなど、特別な付加価値に対する期待が高いのも特徴です。
Z世代の情報収集はGoogleより「タグる」「タブる」が主流
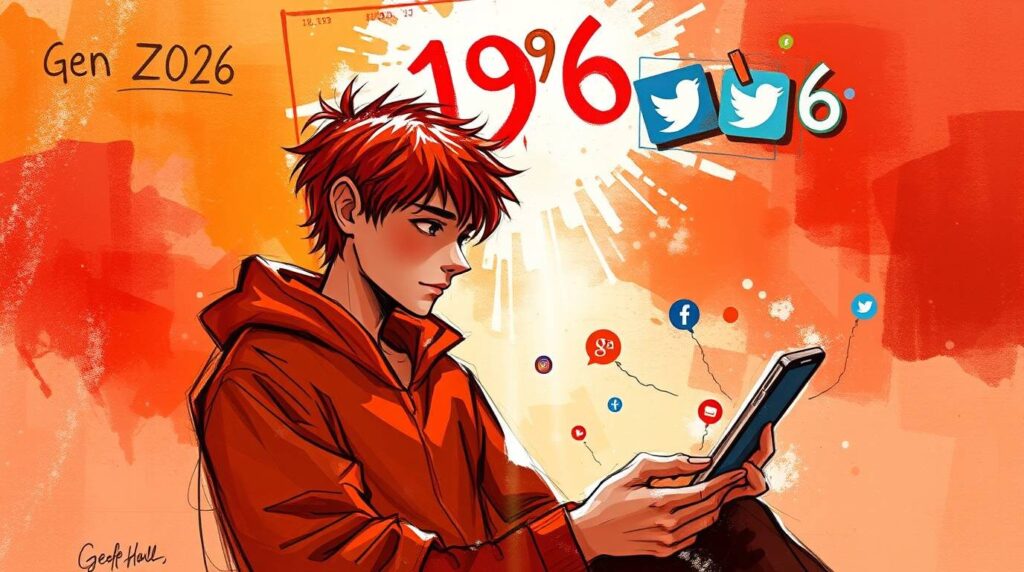
Z世代の情報収集方法は、従来の検索エンジンを使った「ググる」という方法とは大きく異なります。調査の結果、Z世代特有の情報収集法として「タグる」「タブる」という行動が挙げられます。「タグる」とはInstagramでのハッシュタグ検索を、「タブる」は発見タブを閲覧することを指します。Z世代にとって、SNS検索のほうが求めている情報を効率よく入手できる方法なのです。
Z世代は情報収集の際、それぞれのSNSを目的に応じて使い分けています。例えば、情報収集にはInstagramやX(旧Twitter)、知りたいことがあるときはYouTube、動画を見たいときはTikTokというように、場面に応じて最適なプラットフォームを選択する能力に長けています。
また、Z世代は「タイパ」(タイムパフォーマンス)を重視する傾向にあります。NetflixやYouTubeには膨大なコンテンツがありますが、自分の時間は限られているため、動画を見る際には倍速再生を利用したり、音楽を聴くときにイントロを早送りしたりするなど、情報の効率的な消費を心がけています。
興味深いことに、Z世代はSNSを頻繁に利用する一方で、SNSでの投稿内容よりも家族や友人からの情報を信頼する傾向が強いというデータもあります。多くのユーザーがSNSを日常的に利用していますが、そこで得た情報をそのまま信じるのではなく、実際のリアルな人間関係の中で得た情報を重視する傾向があるようです。
1996年生まれのZ世代は、情報リテラシーが高いことも特徴です。インターネット上の大量の情報から、自分に必要な情報を見つけ出し、判断する能力を持っています。また、発信者としての側面も持ち合わせており、SNSでは「映え写真」を投稿して「いいね!」をもらうなど、承認欲求も見られます。一部のZ世代にとっては、「ユーチューバー」や「インフルエンサー」になることが憧れの職業となっています。
Z世代向けのマーケティング手法は従来とは異なる
Z世代に効果的なマーケティング手法は、従来の世代とは大きく異なります。調査の結果、Z世代に向けたマーケティングでは、デジタルマーケティング、SNSマーケティング、体験型キャンペーン、スポンサーシップ、インフルエンサーマーケティングなどが有効とされています。
デジタルマーケティングについては、Z世代のデジタルリテラシーの高さを考慮する必要があります。Z世代は常に情報に触れているため、その人の興味関心に合った魅力的なコンテンツでなければ見てもらえません。パーソナライズされた広告の配信や、短尺の動画コンテンツが効果的です。また、メタバース(仮想空間)を活用したマーケティングも注目されており、アメリカではZ世代の88%がメタバース体験をしたというデータもあります。
SNSマーケティングは、Z世代にリーチするために最も重要な手段の一つです。テスティーの調査によると、Z世代のSNS利用率は中学生で97.3%、高校生で98.9%、大学生で97.9%と非常に高い数値を示しています。企業アカウントの運用とSNS広告の両面から、Z世代に訴求する戦略が必要です。
体験型キャンペーンも効果的です。Z世代はモノよりコト(体験)に価値を感じる傾向があります。例えば、スターバックスの「47 JIMOTO フラペチーノ」キャンペーンは全国47都道府県で異なるフレーバーを楽しめるというもので、Z世代の間で「都道府県スタバ巡り」が流行しました。SNSでの投稿を促すような体験型のキャンペーンが効果的です。
スポンサーシップやインフルエンサーマーケティングもZ世代へのアプローチとして有効です。Z世代は、広告よりも自分が所属するコミュニティ内の情報や、好きなインフルエンサーからの情報を信頼する傾向があります。e-sportsなどのZ世代に親和性の高いコミュニティをスポンサードしたり、Z世代に人気のインフルエンサーとコラボレーションするマーケティング手法が効果を発揮します。
Z世代へのマーケティングでは、誠実さと透明性も重要です。Z世代は企業の社会的責任や環境への取り組みなどを重視し、自分の価値観に合わない企業の製品は選ばない傾向があります。単に製品機能をアピールするだけでなく、企業の理念や社会貢献活動も効果的に伝えることが大切です。
1996年生まれの有名人は様々な分野で活躍中
1996年(平成8年)生まれの有名人は、様々な分野で活躍しています。調査の結果、俳優、アスリート、ミュージシャン、タレント、アナウンサーなど、多岐にわたる業界で1996年生まれの著名人が注目を集めています。
俳優・女優では、橋本愛さん、小松菜奈さん、池田エライザさん、新田真剣佑さん、横浜流星さんなどが1996年生まれです。これらの若手実力派俳優は映画やドラマで主要な役を演じ、Z世代を代表する存在として注目されています。
スポーツ界では、オリンピックのメダリストも多数輩出しています。柔道の東京オリンピック金メダリストであるウルフ・アロン選手、レスリングのパリオリンピック金メダリストの樋口黎選手、フェンシングの松山恭助選手、体操の萱和磨選手や谷川航選手など、世界で活躍するトップアスリートが1996年生まれです。野球では、WBC2023日本代表の岡本和真選手や周東佑京選手、中野拓夢選手、栗林良吏選手も同年生まれです。
音楽やエンターテイメント業界でも、大原櫻子さん(歌手、女優)、佐野玲於さん(GENERATIONS)、ジェシーさん(SixTONES)など多くのアーティストが活躍しています。また、アナウンサーとしては、田村真子さん(TBS)、石川みなみさん(日本テレビ)、篠原梨菜さん(TBS)、大堀彩さん(バドミントン選手)などが同年生まれとして知られています。
1996年生まれの著名人が29歳(2025年時点)となり、それぞれの分野で中心的な役割を担いつつあります。彼らの活躍は同世代の若者にとってロールモデルとなり、Z世代の価値観や感性を社会に広める役割も果たしています。
注目すべきは、これらの有名人が活躍する分野の多様性です。従来の芸能・スポーツ分野だけでなく、YouTuberやインフルエンサーなど新しいメディアで活躍する人も増えています。これはZ世代のキャリア観の多様性を反映していると言えるでしょう。1996年生まれの著名人たちの今後の活躍に、引き続き注目が集まることでしょう。
まとめ:1996年生まれはZ世代に位置づけられる特徴と影響力
最後に記事のポイントをまとめます。
- 1996年生まれはZ世代に属しており、Z世代は一般的に1996年~2012年生まれとされている
- Z世代の名前の由来はアルファベット順で、X世代、Y世代(ミレニアル世代)の次という意味である
- 1996年生まれは平成8年生まれであり、2025年現在で29歳を迎える
- Z世代の前の世代はミレニアル世代(Y世代:1980年~1995年)で、両世代には共通点と相違点がある
- 世代の区分けは研究機関によって若干異なるが、一般的には1996年生まれはZ世代の始まりとされている
- Z世代はデジタルネイティブであり、特にSNSを活用する「真のSNS世代」である
- Z世代の価値観の特徴として多様性の尊重や環境問題・社会課題への関心の高さが挙げられる
- Z世代の消費行動は「エモ消費」「イミ消費」が特徴で、体験や意味を重視する傾向がある
- Z世代の情報収集はGoogleよりも「タグる」「タブる」など、SNSを活用した方法が特徴的
- Z世代向けのマーケティングにはデジタルマーケティング、SNSマーケティング、体験型キャンペーンなどが有効
- 1996年生まれの有名人は俳優、アスリート、ミュージシャンなど多岐にわたる分野で活躍している
- 1996年生まれはZ世代の先駆けとして、社会の中心的役割を担いつつある