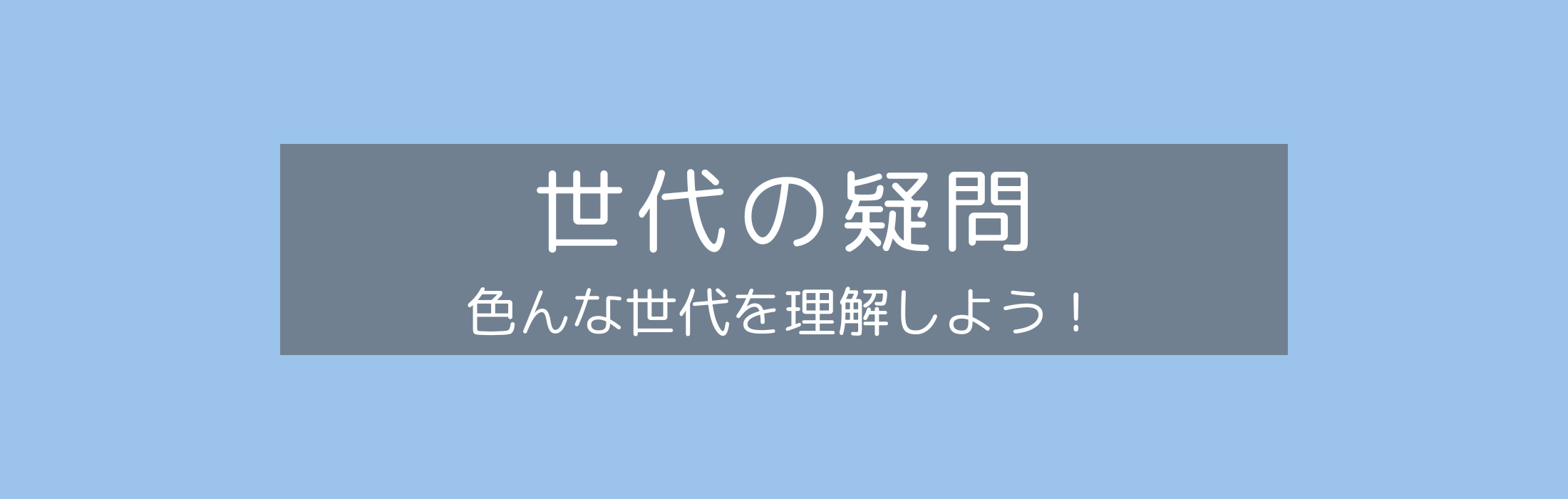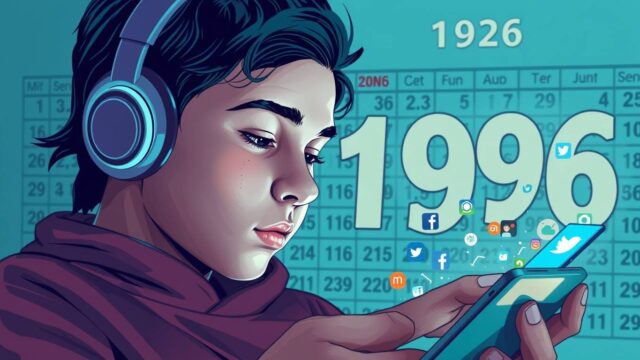2005年生まれの方々にとって、子ども時代に触れた文化や作品は今や懐かしい思い出となっています。現在20歳を迎える2005年生まれの皆さんが小学生だった2010年代前半は、プリキュアシリーズ全盛期、妖怪ウォッチブーム、ニンテンドーDS隆盛期など、今から振り返ると「あの頃」という特別な時代でした。
「懐かしい」と感じるタイミングは人それぞれですが、みんなで「あのアニメ覚えてる?」「このゲーム持ってた!」と盛り上がるのは格別の楽しさがあります。この記事では、2005年生まれの方々が小学生時代に親しんだアニメ、ゲーム、音楽、さらにはガラケー文化まで、懐かしのコンテンツを総特集していきます。
記事のポイント!
- 2005年生まれが小学生時代に親しんだ人気アニメ・特撮シリーズ
- 2005年生まれが夢中になったゲームとおもちゃの数々
- 2005年生まれにとって懐かしい音楽や流行った曲
- 2005年生まれ前後の世代との共通点と違い
2005年生まれが懐かしむアニメやゲームの世界
- プリキュアシリーズは2005年生まれの青春そのもの
- ポケモン世代の記憶は「ダイヤモンド&パール」から「XY」まで続く
- アイカツ!とプリティーシリーズのカード収集が女子の定番だった
- 妖怪ウォッチブームは2005年生まれの小学校生活を彩った
- たまごっちシリーズの進化は2005年生まれと共に成長した
- ニンテンドーDSの名作ソフトは2005年生まれの遊びの中心だった
プリキュアシリーズは2005年生まれの青春そのもの
2005年生まれの方々にとって、プリキュアシリーズは特別な存在です。実は2004年にスタートしたプリキュアは、2005年生まれと同い年と言えるシリーズでした。調査によると、特に人気だったのは『Yes!プリキュア5』や『Yes!プリキュア5GoGo!』、『フレッシュプリキュア!』、そして『ハートキャッチプリキュア!』などのシリーズ。
これらのシリーズは2005年生まれの方々が幼稚園から小学校低学年の頃にちょうど放送されていたため、特に強い思い出として残っています。「キュアマリンに影響されてランドセルの色を水色にした」という証言もあり、子どもたちの生活にも大きな影響を与えていました。
プリキュアの影響は今でも続いており、2023年には『オトナプリキュア』が放送されるなど、視聴者と共に成長し続けるコンテンツとなっています。2024年には『わんだふるぷりきゅあ!』がスタートし、なんと犬が変身するという新たな展開も。プリキュアシリーズは2005年生まれの方々と共に歩み、今でも愛され続けています。
シリーズによって特徴的な変身シーンやフレーズも異なり、「1,2,3,4 プリキュア 5!」「だってそれが永遠不滅 プリキュアよ」といったフレーズは今でも覚えている方も多いのではないでしょうか。プリキュアの歴史は2005年生まれの方々の成長とリンクしており、それぞれの思い出と重なる特別なコンテンツなのです。
バンダイの玩具やなりきりグッズでの遊びも、当時の遊び文化の大きな部分を占めていました。変身アイテムを持って友達と一緒に変身ごっこをした思い出は、2005年生まれの方々にとって共通の青春体験といえるでしょう。
ポケモン世代の記憶は「ダイヤモンド&パール」から「XY」まで続く
2005年生まれの方々にとってのポケモンといえば、『ポケットモンスター ダイヤモンド&パール』から『ポケットモンスター XY』の時代が青春そのものだったようです。調査によると、多くの2005年生まれの方々が「ポケモン観てた!ポケモンやってた!なんなら今もやってる!」と回答しています。
『ダイヤモンド&パール』のゲーム中にある「228ばんどうろ」の音楽は名曲として記憶に残っている方も多いでしょう。アニメに関しては、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』はOPが歴代唯一ポケモンのみの登場というユニークな特徴を持ち、『XY』シリーズの主題歌「XY&Z」は歴代最高と評される名曲でした。
当時の子どもたちにとってポケモンは単なるアニメやゲームではなく、カードゲームやおもちゃ、友達との交換や対戦など、コミュニケーションの重要な手段でもありました。休み時間にDSを持ち寄って対戦したり、カードを交換したりする光景は、2005年生まれの小学校生活の風景として鮮明に記憶に残っているでしょう。
ポケモンの世界観は、子どもたちの想像力を刺激し続けました。「ガブリアスの種族値は102」のような専門的知識をマスターし、より強いパーティを作るために情報交換する姿は、当時のポケモン好きの子どもたちの日常でした。
2023年には、長年主人公だったサトシから新世代の主人公「リコ」と「ロイ」にバトンタッチされましたが、2005年生まれの方々にとっては、サトシこそがポケモンの顔という認識が強いかもしれません。ポケモンは時代と共に進化しながらも、世代を超えて愛され続けるコンテンツとして今も輝き続けています。
アイカツ!とプリティーシリーズのカード収集が女子の定番だった

2005年生まれの女子にとって、「アイカツ!」シリーズと「プリティーシリーズ」は特別な思い出として刻まれています。『アイカツ!』は2012年からスタートし、続く『アイカツスターズ!』『アイカツフレンズ!』『アイカツオンパレード!』『アイカツプラネット!』と展開されました。調査によると、これらのシリーズは単にアニメを見るだけではなく、カード収集やアーケードゲームとしても大流行したようです。
「休日になる度に100円を握りしめてゲームセンターに向かっていた」という証言は、当時の熱量を物語っています。友達とのカード交換の熾烈な交渉、「ちゃお」というキッズ雑誌のアイカツカード全員プレゼントに応募する経験、高難易度のスペシャルアピールのボタン連打は親に託すという工夫など、アイカツ文化は子どもたちの間で独自の進化を遂げていました。
一方、プリティーシリーズも「プリズムストーン」という架空のショップを中心に展開され、『プリパラ』『キラッとプリ☆チャン』『ワッチャプリマジ!』と続いていきました。2023年4月からは新シリーズ「ひみつのアイプリ」へと進化しています。「レインボーライブ」の「gift」や「チェキ☆ラブ」など、プリティーシリーズの楽曲も熱心なファンを生みました。
これらのシリーズが面白いのは、韓国のアイドル文化とも連動していた点です。「PURETTY」は「Prizmmy☆」と同時に誕生した韓国のアイドルグループで、姉貴分とされた「KARA」は「ミスター」や「GO GO サマー!」などの楽曲で一世を風靡していました。アニメの世界と現実のアイドル文化が融合する流れは、当時のトレンドの取り入れの速さを表しています。
アイカツ!シリーズは2023年に10周年を迎え、記念映画も公開されました。かつて熱中した子どもたちが成長した今でも愛される作品として、2005年生まれの青春の記憶の中に深く刻まれています。
妖怪ウォッチブームは2005年生まれの小学校生活を彩った
2005年生まれの方々が小学生だった2010年代前半、爆発的な人気を誇ったのが『妖怪ウォッチ』でした。調査によると、「3DSで狂ったようにやってました!」「妖怪メダル集めてた!」という声が多く聞かれ、当時の社会現象的な流行を裏付けています。
妖怪ウォッチは2014年に特に人気が急上昇しました。この年、2005年生まれの方々は小学4年生頃。アニメも大人気で、印象的なエンディングテーマとして「ようかい体操第一」やニャーKB with ツチノコパンダによる「アイドルはウーニャニャの件」、Dream5+ブリー隊長による「ダン・ダン ドゥビ・ズバー!」などが子どもたちの間で大流行しました。
特にビリーズブートキャンプを模したエンディングは、子どもたちの間で真似されるほどの人気を博しました。ゲームの人気に加え、妖怪メダルという物理的なコレクションアイテムが存在したことも、ブームを加速させた要因の一つでしょう。友達との交換や収集の喜びが、子どもたちの日常に彩りを添えていました。
2014年という年は、妖怪ウォッチだけでなく、アナと雪の女王(アナ雪)の公開、STAP細胞騒動、例の号泣会見、お笑いではラッスンゴレライやあったかいんだからぁ、ダメよ〜ダメダメなどが流行した濃密な1年でした。2005年生まれの方々の小学校時代の思い出は、これらの社会現象とも深く結びついています。
妖怪ウォッチの魅力は、日本の伝統的な「妖怪」という概念を現代的にアレンジし、子どもたちにわかりやすく提示したことにあります。ジバニャンやウィスパーといったキャラクターは、当時の子どもたちのアイコンとして大きな存在感を放っていました。現在は以前ほどの熱狂は見られませんが、2005年生まれの方々の心の中に特別な思い出として残り続けています。
たまごっちシリーズの進化は2005年生まれと共に成長した
たまごっちは、2005年生まれに限らず多くの世代にぶっ刺さるゲーム・おもちゃシリーズでした。調査によると、2005年生まれの方々が触れたのは「たまごっちiDL」や「おうちdeたまごっちステーション」などのバージョンだったようです。たまごっちは1996年に初登場してから進化を続け、2005年生まれの方々が小学生の頃には最新型として親しまれていました。
たまごっちの育成は学校生活の中で大変なこともありました。「学校に持っていくわけにもいかず、また親に託すという方法も思いつかなかった私。大抵帰ってくると餓死しているか部屋が大変なことになっているかの2択でした」という証言からは、デジタルペットの育成の難しさと愛着が伝わってきます。
たまごっちはゲームだけでなくアニメも人気でした。木曜日に「たまごっち→アイカツ→ポケモン→ナルト」という流れでアニメを観ることが習慣になっていた子どもも多かったようです。アニメでは「たまハートをひたすら集めていたら突如たまごっち星がタマゴ化という現象に侵略される」というドラマチックな展開や、「ゆめキラドリーム」で流れていた「キラキラ☆ドリーム」という歌が特に印象に残っていると言います。
たまごっちシリーズは現在も進化を続けており、2023年7月13日には「たまごっちユニ」が発売されています。懐かしいキャラクターに新たな機能が加わり、新世代の子どもたちにも愛されているのです。
たまごっちの魅力は、単純なデザインながらも豊かな感情移入ができる点にあります。小さな画面の中の小さな生き物に責任を持ち、成長を見守る体験は、2005年生まれの方々にとって大切な思い出となっているのではないでしょうか。
ニンテンドーDSの名作ソフトは2005年生まれの遊びの中心だった
2005年生まれの方々が小学生だった頃、ニンテンドーDSは子どもたちの遊びの中心でした。2004年12月に発売されたニンテンドーDSは、2005年生まれの方々が成長するのとちょうど同じタイミングで進化していきました。調査によると、2004年から2005年にかけて発売された主要ソフトには、『スーパーマリオ64DS』『さわるメイドインワリオ』『ポケモンダッシュ』『大合奏!バンドブラザーズ』などがありました。
2005年以降も『脳を鍛える 大人のDSトレーニング』『nintendogs』『エレクトロプランクトン』『タッチ!カービィ』など、タッチペンを活かした革新的なソフトが次々と登場。特に2005年12月に発売された『マリオカートDS』と『マリオ&ルイージRPG2』、そして『もっと脳を鍛える 大人のDSトレーニング』は、家族みんなで楽しめるゲームとして大ヒットしました。
2005年11月に発売された『おいでよ どうぶつの森』は、リアルタイムで進行する生活シミュレーションゲームとして革新的でした。季節の変化や特別なイベントが現実と連動して起こるシステムは、子どもたちに強い没入感をもたらしました。多くの友達と交流するための「村」に関する会話は、休み時間の定番トピックだったことでしょう。
DSの魅力は携帯性の高さにもありました。友達の家に持っていって対戦したり、旅行先に持っていったりと、場所を選ばず遊べる点は当時としては画期的でした。Wi-Fiコネクションを使ったオンライン対戦も可能になり、友達同士の交流の幅が広がりました。
ニンテンドーDSは2011年頃まで主力機として活躍し、後継機のニンテンドー3DSへとバトンタッチ。2005年生まれの方々が小学校高学年から中学生になる頃には、新たなゲーム体験へと移行していきました。しかし、DSで過ごした時間は、2005年生まれの方々の原体験として特別な位置を占めているに違いありません。
2005年生まれと懐かしい音楽や文化的背景
- 2005年生まれに響く懐かしの名曲はドラマやアニメのテーマソングが中心
- ガラケー時代の「ホムペ」文化は2005年生まれの貴重な経験
- 国語教科書に載っていた物語は2005年生まれの共通の思い出
- 2004年と2006年生まれとの共通点と違いから見る2005年生まれの特徴
- 小学校時代の流行語やイベントは2005年生まれの懐かしい記憶の源泉
- まとめ:2005年生まれにとって懐かしいものは青春の宝物
2005年生まれに響く懐かしの名曲はドラマやアニメのテーマソングが中心
2005年生まれの方々が懐かしく感じる楽曲は、主にアニメやドラマの主題歌に集中しています。調査によると、Spotifyには「懐かしい曲〈2005、2006年生まれ向け〉」というプレイリストが存在し、「2004〜2007年生まれぐらいの人が聴いたら『懐かしー!』ってなる曲。当時放送されていたドラマ、アニメ、特撮の主題歌多め」というコンセプトで曲が集められています。
このプレイリストには「Life is SHOW TIME」(Sho Kiryuuin)、「恋」(Gen Hoshino)、「ようかい体操第一」(Dream5)、「360°」(miwa)、「夢をかなえてドラえもん」(Mao)など、2010年代前半に流行した曲が多く収録されています。特に「恋」は星野源の楽曲で、ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の主題歌として大ヒットしました。
アニメソングでは「Switch On!」(Anna Tsuchiya)、「Anything Goes!」(Maki Ohguro)、「JUST LIVE MORE」(鎧武乃風)などの特撮ヒーロー関連の曲も人気です。これらはおそらく「仮面ライダー」シリーズの主題歌と推測されます。また、「XY&Z」(Satoshi/CV: Rica Matsumoto)のようなポケモンの主題歌も懐かしさを感じる一曲として挙げられています。
J-POPでは「友よ 〜 この先もずっと・・・」(Ketsumeishi)、「OLA!!」(YUZU)、「キミに100パーセント」(Kyary Pamyu Pamyu)といった曲も懐かしのヒットソングとして記憶されています。特に2011年の「にんじゃりばんばん」(Kyary Pamyu Pamyu)や2016年の「前前前世」(RADWIMPS)は、映画「君の名は。」の大ヒットと共に世代を超えた人気を獲得しました。
ディズニー映画「アナと雪の女王」の「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」(Takako Matsu)や、「リメンバー・ミー」の「Remember Me」(Hiiro Ishibashi)といった映画主題歌も懐かしさを感じさせる楽曲として挙げられています。
2005年生まれの方々にとって、これらの楽曲は子ども時代のサウンドトラックとして心に刻まれ、聴くだけで当時の記憶が鮮明によみがえる特別な存在なのかもしれません。
ガラケー時代の「ホムペ」文化は2005年生まれの貴重な経験
2005年生まれの方々が中学生から高校生になる2010年代後半、スマートフォンが普及する直前のガラケー(フィーチャーフォン)全盛期がありました。この時代、若者の間で個人のホームページを作る「ホムペ」文化が流行しました。これは2005年生まれの方々が経験した最後のガラケー文化とも言えるかもしれません。
調査によると、ホムペは個人サイトを作成・運営するサービスで、「nano-ナノ-」「モバスペ」「フォレストページ」「@peps!」などの無料ホームページ作成サービスが人気でした。ドメインを取得したりサーバーを借りたりする必要はなく、服を選ぶような気軽さでサービスの機能やデザインを選び、コンテンツを作って遊ぶことができました。
ホムペの主な用途は「友人との交流」と「個人的なブログ」でした。友人同士の交流のためのページには、自己紹介、リアルタイム投稿、日記、写真ライブラリ、BBS(掲示板)、リンクといった機能が備わっていました。特にリンク機能は「リンク数が多い=友達が多い、すごい」という価値観を生み出し、ホムペが流行した理由の一つとなりました。
ホムペをカスタマイズするためにHTMLを独学で学んだ中高生も多く、「素材屋さん」と呼ばれるフリー素材提供サイトから素材を収集してオリジナリティを表現するという文化も生まれました。また、パスワードで保護された「隠しページ」を作り、親しい友人だけに公開するという秘密の交流も行われていました。
ホムペ文化は2015年頃、スマートフォンの個人保有率が50%を超えるとともに衰退し、SNSに取って代わられました。2005年生まれの方々にとって、この文化はデジタルコミュニケーションの転換期を体験した貴重な記憶として残っているのではないでしょうか。
国語教科書に載っていた物語は2005年生まれの共通の思い出

2005年生まれの方々が小学生時代に触れた国語教科書の物語は、世代共通の思い出として心に残っています。調査によると、「大人も懐かしい、小学校と中学校の国語教科書に掲載されていたお話の絵本と児童書」が多数存在しており、これらは世代を超えて読み継がれてきました。
小学校低学年で出会う物語としては、「おおきなかぶ」(A・トルストイ再話)、「ふたりはともだち」(アーノルド・ローベル)、「スイミー」(レオ・レオニ)などがあります。特に「スイミー」は「小さな黒い魚スイミーは、広い海で仲間と暮らしていました。ある日、仲間たちが大きな魚にみな食べられてしまいました。一匹だけ残ったスイミーは……」という物語で、1977年から小学1・2年生の教科書に掲載され続けてきました。
小学校中学年では「スーホの白い馬」(大塚勇三)、「手ぶくろを買いに」(新美南吉)、「いっぽんの鉛筆のむこうに」(谷川俊太郎)などが登場します。「スーホの白い馬」はモンゴルに伝わる楽器、馬頭琴の由来を描いた物語で、1965年から小学2年生の教科書に掲載されてきた長寿作品です。
高学年になると「車のいろは空のいろ 白いぼうし」(あまんきみこ)、「やまなし」(宮沢賢治)、「カレーライス」(重松清)などの作品に出会います。「やまなし」は「クラムボンはかぷかぷわらったよ」など不思議なフレーズで知られる作品で、1971年から小学6年生の教科書に掲載されてきました。
中学校では「少年の日の思い出」(ヘルマン・ヘッセ)や「おーい でてこーい」(星新一)などの作品が登場します。「少年の日の思い出」は蝶の標本を巡る話で、なんと1947年から中学1年生の教科書に掲載され続けている超ロングセラー作品です。
これらの物語は教科書という媒体を通じて出会ったからこそ、同世代で共通の思い出として語り合うことができます。2005年生まれの方々にとって、国語教科書の物語は懐かしさと共に、読解力や想像力を育んだ大切な教材だったのでしょう。
2004年と2006年生まれとの共通点と違いから見る2005年生まれの特徴
2005年生まれの方々は、2004年生まれと2006年生まれの間に位置する世代です。調査によると、「2004年,2005年生まれへ」「0405lineの皆様、おめでとうございます」といった表現で両者をまとめて扱うケースが多く見られ、特に近い関係性があることがわかります。
共通点としては、アニメやゲームの嗜好がかなり重なっています。プリキュア、ポケモン、アイカツ!、プリティーシリーズ、妖怪ウォッチ、たまごっちなど、2004年から2006年生まれにかけて人気だったコンテンツはほぼ同じです。また、ニンテンドーDSやガラケーなどのデバイスも共通の思い出となっています。
特に2005年生まれと2004年生まれは「0405line」と呼ばれることが多く、2025年に成人式を迎える同期として括られることが多いようです。「18歳成人式が最初に行われる世代」としても注目されています。「ハタチになるのはいいけれど、大人になった実感が全然湧かない…!」という感覚も共有されているようです。
一方で、微妙な違いも存在します。2004年生まれの方々は小学校入学時にはすでにニンテンドーDSが発売されていたのに対し、2006年生まれの方々は小学校低学年の頃にはニンテンドー3DSに移行する時期と重なっていました。また、スマートフォンの普及時期による影響も世代間で微妙に異なります。
音楽の面では、2004年生まれの方々は2010年頃の楽曲を小学校低学年で、2015年頃の楽曲を小学校高学年で体験しました。一方、2006年生まれの方々は同じ曲でも1〜2年遅れて体験しているため、同じ曲に対する感覚が微妙に異なる可能性があります。
こうした微妙な違いを超えて、2004年から2006年生まれの方々は「平成後期生まれ」として共通の文化を共有しています。2005年生まれの方々は、そのちょうど真ん中に位置する世代として、両者の特徴を併せ持つ特別な存在と言えるでしょう。
小学校時代の流行語やイベントは2005年生まれの懐かしい記憶の源泉
2005年生まれの方々が小学生だった2010年代初頭から中頃は、特徴的な流行語やイベントが数多く存在しました。調査によると、特に2014年は「アナ雪」の公開、「STAP細胞騒動」、「例の号泣会見」、お笑いでは「ラッスンゴレライ」、「あったかいんだからぁ」、「ダメよ〜ダメダメ」などが小学校を席巻した「濃すぎる」1年だったようです。
子どもたちの間では、プリクラを撮ることが流行っていました。特に「2娘イチ(にこいち)」「仲仔(なかよし)」といった独特の表記が定番の落書きとして広まり、やがて「仲よし仔(なかよしこ)」「双仔(ふたご)」といった派生語も増えていきました。プリクラはホムペの「写真ライブラリ」機能とも連動し、「インターネットプリクラ帳」のような使われ方もしていました。
テレビの視聴習慣も特徴的で、「木曜日にたまごっち→アイカツ→ポケモン→ナルトの流れでアニメを観ること」や「金曜の妖怪ウォッチ→ドラえもん→クレヨンしんちゃんの流れ」といったパターンが定着していたようです。こうした視聴習慣は、同世代の共通体験として強く記憶に残っています。
学校生活では、カードゲームやゲームの交換・対戦が休み時間の定番でした。特にポケモンカードや妖怪ウォッチのメダル交換は、友達関係を築く重要なコミュニケーション手段となっていました。「高難易度のスペシャルアピールのボタン連打は親に託す」といった、親を巻き込んだゲームプレイの工夫も当時ならではの思い出です。
インターネット文化では、YouTubeの普及により動画視聴が一般化し始めた時期でもありました。「カゲロウプロジェクト」のような音楽を中心としたマルチメディアコンテンツや、「ニコニコ動画」での音楽・動画体験は、当時の中高生文化に大きな影響を与えました。
これらの流行語やイベントは、2005年生まれの方々の小学校時代の記憶を彩る重要な要素であり、「あの頃」を思い出す懐かしさの源泉となっています。
まとめ:2005年生まれにとって懐かしいものは青春の宝物
この記事のポイントをまとめます。
- 2005年生まれの方々にとってプリキュアシリーズは同い年のコンテンツであり、特に『Yes!プリキュア5』や『ハートキャッチプリキュア!』は青春と共に歩んだ作品
- ポケモンは『ダイヤモンド&パール』から『XY』までが2005年生まれの中心世代で、ゲーム、アニメ、カードなど多角的に親しまれた
- アイカツ!とプリティーシリーズは女子を中心に大流行し、カード収集やアーケードゲームが友達同士の交流の場となった
- 妖怪ウォッチは2014年に社会現象となり、「ようかい体操第一」や「ニャーKB」などの楽曲も含めて2005年生まれの小学校生活を彩った
- たまごっちは世代を超えて愛されるデジタルペットで、「たまごっちiDL」などが2005年生まれ世代の友達との会話の話題になった
- ニンテンドーDSは2005年生まれの方々が成長する時期と重なり、『マリオカートDS』や『おいでよ どうぶつの森』などの名作が遊びの中心だった
- 2005年生まれに響く懐かしの名曲はアニメやドラマの主題歌が多く、「恋」や「前前前世」などが特に記憶に残っている
- ガラケー時代の「ホムペ」文化は友人との交流や創作活動の場として機能し、HTMLを独学で学ぶきっかけにもなった
- 国語教科書に掲載された「スイミー」「スーホの白い馬」「やまなし」などの物語は世代共通の思い出となっている
- 2004年から2006年生まれは文化的に近い関係にあり、特に2004年と2005年生まれは「0405line」として括られることが多い
- 2010年代初頭から中頃の流行語やイベント、プリクラやテレビ視聴習慣は2005年生まれの懐かしい記憶の源泉となっている
- 2005年生まれの方々にとって懐かしいものは単なる過去の思い出ではなく、アイデンティティの形成に関わる大切な青春の宝物である